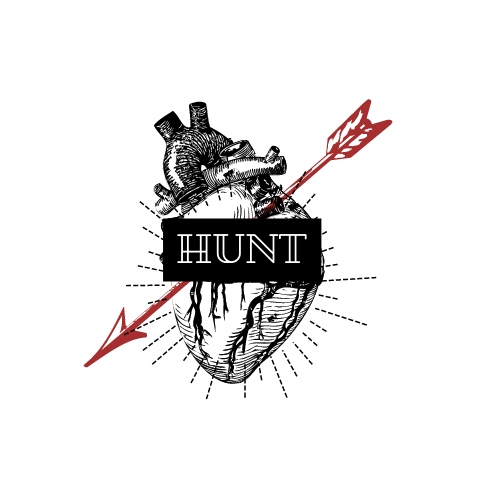7. Make A Wish
Caption
誕生日パーティの夜にテロリストに襲撃された七歳の僕を、パパの友人のルーク・ハントが助けにくる話。
成分表:ネームレス男主夢 | 卒業後 | オリキャラ | 殺人・流血
Make a wish. 火を灯したケーキを前にそう言われ、僕は数秒間目を瞑って願ったあとふうっと七本の蝋燭を吹き消した。部屋が暗くなるのと同時に、鳴り響くパンッという破裂音。クラッカーなら僕が部屋に入ってきたときにも鳴らしていたのに。そう不思議に思いながら上げた頭は、大きな手によってテーブルの下に抑え込まれた。
再び聞こえた破裂音。そのとき地面に身体を伏せた僕の目の前に、なにかがどすんと大きな音を立てて倒れてきた。それは僕が五歳の頃からバイオリンを教えに来てくれている、エリオット先生だった。いつもの優しい笑顔からは想像もできないような虚ろな目。こめかみのあたりに開いた小さな穴からドクドクと流れ出る血が、木張りの床を赤く染める。
そこでようやく僕の耳が正常に働き始め、部屋中から悲鳴や泣き叫ぶ声が聞こえてきた。少し遅れて、あの破裂音がクラッカーなどではなく銃声であり、エリオット先生は死んでしまったのだということに気づく。人々が逃げ回る音に、食器や調度品が割れる音。テーブルの下で身体を伏せたまま呆然としていた僕の襟首を、誰かがつかんだ。
「無事ですか?」
「ラリー」
「正確にはわかりませんが、敵の数が多い。ここから出ましょう」
「うん」
頭を低くしたまま、ラリーの陰に隠れるようにぴったりくっついて移動する。
僕の父は、為政者だ。僕のパパとして過ごす時間よりMr. Presidentと呼ばれる時間のほうが長いほど忙しい人だが、彼が僕のことを愛してくれていることはよく知っている。
二年前に事故でママを喪ってから、どうしても一人で過ごす時間が増えた。でもパパはできるだけ僕と一緒に過ごせるように考えてくれたし、僕にはエリオット先生やラリーがいた。
ラリーは僕のボディガードだ。僕が生まれたときからずっと、僕のことを守ってくれている。昔一度だけ、ラリーに尋ねたことがある。「やっぱりラリーも、子供のお守りよりパパの警備のほうがいいの?」と。それは僕が今よりずっと幼かったのと、その前の週に臨時でボディガードを担当していた人がそう愚痴っていたのを聞いてしまったからだ。
お気に入りのテディの耳を引っ張りながらそう言うと、ラリーは車のバックミラー越しに僕を見つめてしばらく考えてから口を開いた。
「確かに私はあなたのお父上に頼まれてあなたの警護をしていますが、この仕事を「お守り」だと思ったことはありません」
「でも……」
「あなたは私がそばにいて、迷惑ですか?」
「ううん。ラリーと一緒にいるの、楽しいよ。ラリーはかっこいいし、いろんなことを知っているし」
「私もです」
「えっ?」
「あなたが私と一緒にいて楽しいと思うように、私もあなたをそばで守ることができて嬉しいんですよ」
そのときはラリーが嬉しいならよかったなぐらいにしか思わなかったが、今になって振り返ると僕にとってはあれが「生まれて初めて一人の人間として扱ってもらった」瞬間だった。もちろんラリーの雇い主はパパであって僕ではなく、彼は仕事だから僕を守ってくれている。しかしあの日以来ラリーは僕にとってただのボディガードではなく、よき友人であり、先生でもあり、同時に年の離れた兄のような存在となった。
招待客たちが逃げ惑う中、長い廊下を駆け抜ける。背後で聞こえる発砲音。斜め前で花瓶が砕け散り、聞きなれない怒鳴り声が響き渡る。
「ガキは殺すな」
彼らの狙いは僕で、それは僕にパパの弱みとしての利用価値があるからだ。この家に生まれた以上いつかこういうことがあるかもしれないとは思っていたし、覚悟はしていたつもりだった。
脳裏に浮かぶのは、エリオット先生の虚ろな瞳。僕のせいで人が傷つき、死んでしまった。僕が誕生日パーティなんて開いたから。僕なんかと、関わってしまったから。
「玄関はダメです。他の出口も抑えられています」
「あとは向こうにも魔法士がいるようで……おそらくソイツをなんとかしなければ屋敷内では魔法が使えないかと」
頭上から聞こえたその声で、僕は現実に引き戻された。顔を上げると、他のセキュリティたちと話しながらこちらをじっと見下ろすラリーと目があう。飛び交う銃弾と悲鳴。みんなが銃を撃ち返しながら確保してくれた退路を進む。
二階へと続く階段を駆け上がるのと同時に聞こえる、パラララと連続する種類の違う銃声と、人が倒れる音。辺りに充満する硝煙と血のにおいが、僕の呼吸を阻害する。
一体どれだけの人が死んだんだろう。気づけば悲鳴は聞こえなくなり、屋敷の中はまるで何事もなかったかのように静まり返っていた。
出口が使えない今、僕たちが目指すべきは二階にある書斎。その本棚の奥に隠されたセーフルームに逃げ込み鍵をかけてしまえば、よっぽどのことがない限り身の安全を守ることができる。生まれたときからそう聞かされていたし、避難の練習だって何度もしてきた。
でも、怖かった。割れたガラスを踏み鳴らさないよう慎重に歩みを進める足は震え、カラカラに乾いた喉が痛む。
「もう少しで応援が来ます」
だからそれまでもう少し我慢してください。そのとき、僕を気遣うように告げられたその言葉をかき消すように一発の銃声が鳴り響き、ラリーの身体が大きく傾いだ。
「ラリー、」
「……ッ!」
柱に隠れるようにして床に崩れ落ちながら、ラリーが廊下の奥に向けて発砲する。すると遠くで誰かが倒れ、その奥から「こっちだ!」と叫ぶ声と複数の人間が階段を上がる音が聞こえてきた。
「ラリー、血が……」
赤く染まった太腿を押さえようと伸ばした手を、ラリーが制する。
「ここは任せてください」
「でも、」
痛みに顔を歪めながら、ラリーがまっすぐ僕を見た。近づいてくる足音。僕が優先すべきは自分の身の安全であり、ここに留まることは僕がこの場で一番とるべきではない行動だ。僕がここにいてもどうにもならないどころか、足手まといにしかならない。そんなことはわかっている。頭ではそう理解しているのに、身体が動かない。
「行って!」
そんな僕を見つめたまま、ラリーが先程よりも強い口調でそう言った。僕は逃げなくてはならない。僕のためだけではなく、パーティーに来てくれた人たち、ひいてはこの国の人たちみんなのために。
「……またあとでね、ラリー」
「……ええ、またあとで」
無理やり笑顔を浮かべてラリーにそう別れを告げてから、僕は再び書斎を目指して走り始めた。背中で銃のマガジンを再装填する音を聞きながら、僕は振り返ることなく廊下を走る。泣いたらダメだ。そう思うのに僕の目からは涙が流れ、呼吸のために開いた口からは嗚咽が漏れた。
転びそうになりながら廊下の奥を右に曲がって、パパの書斎に飛び込む。同時に廊下の向こう側から聞こえてくる発砲音。その場で叫びだしそうになるのを、唇を噛み締めて我慢する。
書斎の左側にある本棚。その上から三段目に置かれている時計に僕の虹彩を認証させれば、セーフルームの鍵が開く。僕が震える手で棚をつかんで時計を覗き込もうとしたとき、部屋の外で誰かがこちらに向かって走ってくる音が聞こえた。どうしよう。生態認証を使っている時間はない。咄嗟に書斎の中心に置かれた大きな机の下に身体を滑り込ませた瞬間、ギイッと重い扉が軋ませて誰かが部屋の中に入ってきた。
「……かくれんぼは終わりだ」
恐怖で声を漏らしてしまいそうな口を手で覆い、机の下でぎゅっと身体を縮こまらせる。こわい。みんな死んでしまった。エリオット先生も、きっとラリーも。爆発してしまいそうなほど激しく脈打つ心臓。その音が悪い奴にまで聞こえてしまいそうで、僕は空いたほうの手で胸のあたりをぎゅっとつかんだ。こわい。パパ。ラリー。僕が誕生日パーティなんて開いたから。僕が、この世に生まれてしまったから。
……誰か助けて。
ぽろぽろと零れた涙が僕の手を濡らし、床に黒い染みを作ったそのとき。突然きこえたくぐもった声と人が揉みあうような音。数秒間続いたそれは、なにかが折れるような鈍い音によって終わりを迎え、室内に静寂が訪れた。
一体なにが起きたのだろう。口元を押さえたまま息を殺して室内の気配を探っていると、一拍おいて、ぎしりと木張りの床が鳴った。静まりかえった部屋の中、誰かがゆっくりとこちらへ近づいてくる。もしもこれがラリーだったら、真っ先に声をかけるはず。だからそこにいるのは僕の知らない誰かだ。
逃げるチャンスは一度だけ。パパの机は大きいから、反対側から抜け出すことができれば部屋から出られるはず。いつでも走りだせるように体勢を整え、足音がどちらからやってくるのか耳を澄ませていた僕の頭上にぬっと現れた黒い影。絶望しながら顔を上げると、そこでは銃を構えた男でも覆面姿の男でもなく、パーティ用のスーツに身を包んだ金髪の男がこちらを覗き込んでいた。
「遅くなってすまない、mon poussin」
「……ルークさん?」
困惑したまま目の前に差しだされた皮手袋に覆われた手をとると、太い腕が僕を机の下から引っ張り出した。ルークさん。パパの学生時代からの友人で僕の名付け親でもある彼は、時々ふらっとうちに遊びに来てはいろんな話を聞かせてくれる不思議な人だった。
おそるおそる立ち上がると、ルークさんの後ろに転がる武装した男の姿が目に入る。さっきの物音はルークさんが? 丸腰で、武装した相手を一人で? 脳内で様々な疑問が渦巻くなか「どうしてここに?」と問いかけた瞬間。部屋の中が真っ暗になって、僕の口から悲鳴が漏れた。
屋敷の電気を落とされてしまったのか、突然訪れた暗闇。なにも見えないことに焦り、恐怖していると、部屋の中に複数の人間が飛び込んでくる音が聞こえた。
「そこから二歩、後ろにさがって」
暗闇のなか、さっきまで目の前にいたはずのルークさんの声が耳元で聞こえたことに驚きながら、指示通り二歩後ろにさがる。
連続する射撃音と、マズルの光。暗視スコープでもつけているのか、部屋に入ってきた者たちにはこちらの姿が見えているらしい。「いたぞ」という声に身を竦ませると、また耳元でルークさんの声が聞こえた。
「左に二歩動いて、その場でしゃがんでじっとしているんだ。いいね?」
うん、と返事をする前に慌てて身体を動かせば、暗闇のなかでルークさんが「C'est bon」と笑った。
聞こえてくるのは銃声、叫び声、なにかがぶつかりあう音、なにかが折れる音……そしてなにか重いものが地面に落ちる音。再び部屋のなかに静寂が訪れたとき、眩しい明かりが僕を照らした。
「ルークさん、大丈夫!?」
「oui! ああ キミこそ怪我はないかい?」
「僕は大丈夫、だけど……」
懐中電灯の眩しさに目を細めながら、地面に横たわる身体を調べるルークさんを見つめる。きっと彼らはみんな死んでいるのだろう。目の前で人が五人も死んでいるというのに、僕は目の前の光景をどこか他人事のように眺めていた。
「どうしよう、本当なら予備の電源がつくはずなのに」
一向に明るくならない室内。魔法も封じられている今、電力が戻らなければセーフルームを使うことはできない。
悪い奴らが全部で何人いるのかはわからないが、いくらルークさんが強くても一人ではどうしようもないだろう。ひとりぼっちではないことで気が緩んだのか、止まったはずの涙がまたぽろぽろと零れてくる。慌ててそれを腕で拭っていると、装備を剥ぎ終えたルークさんが僕と目線をあわせるようにしゃがみこんで壁に飾られたパパの狩猟弓を指さした。
「……あの弓を借りても?」
「え? あ、うん……でも、銃じゃなくていいの?」
「もちろん、銃も持って行くよ。でもこういうときこそ手に馴染む物のほうがいい」
今さっき人を殺したとは思えないほど落ち着いた様子のルークさんが、僕の前に小型のピストルを差し出す。使いかたは知っているね?使わなくていい。でもいざというときのお守りに持っておこう。そう言って手渡された銃を、黙ってベルトに挟み込む。聞きたいことはたくさんあるけど、今はルークさんについていくしかない。
「そういえば、さっきの質問の答えだけれど」
準備を整えて部屋から出る直前、スーツ姿で矢筒を背負ったルークさんがくるりと僕のほうを振り返る。
「招待状をもらったからね」
そう言って胸元から僕が送った誕生日パーティの招待状を取り出すと、ルークさんは「ではキミの誕生日を取り戻しに行くとしようか」と、また朗らかな笑みを浮かべた。
この作品を共有

👏waveboxで拍手 💌フォームで感想
読んだよ!報告、感想とても嬉しいです!ありがとうございます!