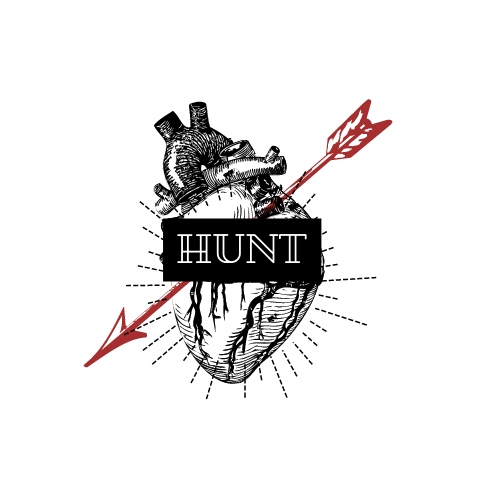6. Man In the Mirror
Caption
他人に成りすますことが趣味の役者の男が、ルーク・ハントに成りすまそうとする話。
成分表:ネームレス男主夢 | 同級生 | カメレオン俳優
僕が最初に銀幕デビューを果たしたのは、まだ首も座っていない赤ん坊だったときのことだった。自分の意思でとは言い難い形で演技の世界に入ったわけだが、この仕事は親が思っていたよりもずっと僕に向いていたようで、NRCに入学した今でも僕は学生生活の傍ら役者として演技の仕事を続けている。
人は僕のことをカメレオン俳優や天才役者なんて仰々しい肩書きで呼ぶが、実際にはそんな大層な人間ではない。ただ少し、人より役柄に没入しやすいだけだ。最近は流石に加減ができるようになってきたが、昔は現場を離れたあとも役が抜けずに困ったりもした。
そもそも僕がそんな性質であるのは、生まれ持ったユニーク魔法をうまく使うために磨いた観察眼と身体表現の力のおかげだった。
そんな僕が演技の練習も兼ねてこの学園でこっそり行っていることがある。僕のユニーク魔法を使って依頼人の憧れの人や憎む相手に姿を変え、その願いを叶えるというものだ。人の欲とは恐ろしいもので、大事にならないよう秘密裏に行っているにもかかわらず、これがなかなか需要がある。
依頼を受けたら、まず一週間かけてじっくりと対象を観察する。ターゲットにバレないようにあとを追い、同じものを食べ、同じように生活し、ときには部屋に侵入して徹底的に嗜好や習慣を探って自分の身体に「他人」を馴染ませていく。そうすれば大体週の中ほどでターゲットのイメージが身体に馴染んでくるので、今度は癖をトレースし、内面をコピーしていく。
ターゲットがどんな人生を歩んできて、どんな考え方をするのか。その思考を読んで解析し、同じように考える。そのためには周りの人間への聞き込みや調査も怠らない。そんなことを繰り返していても怪しまれないのは、ひとえに素の僕が他人の記憶に残らないレベルで没個性的であるからだった。
そして七日目。依頼人と顔をあわせる約束の日。この時点で大体の依頼人は僕の顔を見た瞬間に「あの人が現れたのかと思った」なんて言う。魔法を使っていなくても、歩き方から視線の動かしかた、呼吸の仕方やわずかな発音の癖まで完全にターゲットの真似をしているからだ。そして最後に僕のユニーク魔法「蒼の隣人」を使って姿を変えて「見せ」れば、できあがり。
憧れのあの人に愛の告白を行ったり、抱いてくれと目を潤ませて縋って来たり。流石に命の危険がありそうな依頼は受けないことにしているが、面と向かってなじられたり地面に這いつくばった状態で頭を踏みつけられたこともある。
そこまでして何故そんなことを続けるのか? 金のため? いや、金なら演技の仕事で十分にもらっている。答えは簡単。単純に、自分以外の人間に成り代わることもそれによって露わになる欲望を見ることも面白いからだ。
そんなある日「ポムフィオーレ寮の副寮長になってほしい」という依頼が舞い込んできた。特に断る理由もないので引き受け、いつものように「観察」を開始して三日。僕は困っていた。
ポムフィオーレの副寮長であるルーク・ハントという男。代々狩人の家系に生まれ、人間離れした身体能力を持ち成績も優秀。少し変わり者ではあるようだが、悪い噂などもなく人柄もよい。周りの人間から情報を集めながら観察を続け、身体的な癖や周りからの評価はつかめてきた。しかし一向にその中身が見えてこないのだ。
だから四日目の昼、僕は彼が授業を受けているタイミングを見計らってルークの部屋に侵入することにした。
きちんと整理された、落ち着いた印象の部屋。壁には狩猟に使われる道具が美しく並べられている。クローゼットの中の衣類や、机の上に並べられた書籍。それらをじっくり眺めながら、「この部屋の主は一体何を考え、どんな生きかたをしているのだろう」と考えていたそのときだった。僕の背後で、部屋の扉がゆっくりと開く音が聞こえたのは。
「探し物は見つかったかな?」
草原に吹くそよ風のように穏やかな声。後ろに立っているだろう相手からは怒りも敵意も感じられないのに、僕は自分の背中を冷たい汗が伝うのを感じた。
「……残念ながら、まだ見つかっていないんだ」
ぐっと下腹部に力をいれそう言いながら、なるべく無害そうな印象を与える笑顔を浮かべて振り返る。
部屋の入り口を塞ぐように壁にもたれたルークの視線に射抜かれ、足が震えそうになるところを必死に耐える。今までたくさんの舞台に立ち、様々な人間と対峙してきた。しかしこんなに緊張したのは、生まれて初めてのことだった。
「なにか手伝えることは?」
「そうだな……」
役者をやっていてよかったと、心の底から思った。「他人に見せたい姿」を見せる方法を知らなければ、僕はこの場で膝から崩れ落ちて泣くことすらできずにただ震えていたに違いない。
「よければ、君と話をしてみたいのだけれど」
「……ダミアンだね」
「……なんだって?」
「いまのキミのその表情と、台詞回しだよ。2013年にキミが「さよならも言わずに」という映画で演じたダミアンと同じものだ」
緩やかに弧を描く、ルークの薄い唇。口から零れ出しそうな悲鳴を飲みこんで、同じように口角を上げてみせる。
「……観てくれたんだ。嬉しいよ」
心臓がバクバクと早鐘を打つ。ルークの指摘は正しかった。「よければ、キミと話をしてみたいのだけれど」それは僕が主人公の友人役として出演した映画の中で口にした台詞。ダミアンという名の、冒頭三十分で事故によってこの世を去る、おそらくほとんどの観客の記憶に残らないだろう脇役の台詞。
「Bien sur! キミの出演している作品は全て観させてもらったよ」
「君がそこまで僕の熱烈なファンだったとは……」
「『サインは必要か?ただし転売はするなよ、売れねえからな』」
それは、僕が去年舞台で演じた落ち目の俳優の台詞だった。
「は、はは……驚いたな」
何故、一体いつからバレていた。心の中に渦巻く、焦りと恐怖。それと同時に、僕は確かに喜びを感じていた。さっきから、初めてのことばかりだ。トレースできない相手に出会うのも、僕が過去に出演した全ての作品と役柄、そしてその台詞まで記憶している相手に出会うのも。
「探し物が見つかったかもしれない」
興奮で声が掠れる。感情を読みとることのできないルークの緑色の瞳に映るのは、借り物ではないヘタクソな笑みを浮かべた僕の姿。鏡のようなその瞳に映し出された僕の瞳は、欲望の色に濡れていた。
この作品を共有

👏waveboxで拍手 💌フォームで感想
読んだよ!報告、感想とても嬉しいです!ありがとうございます!