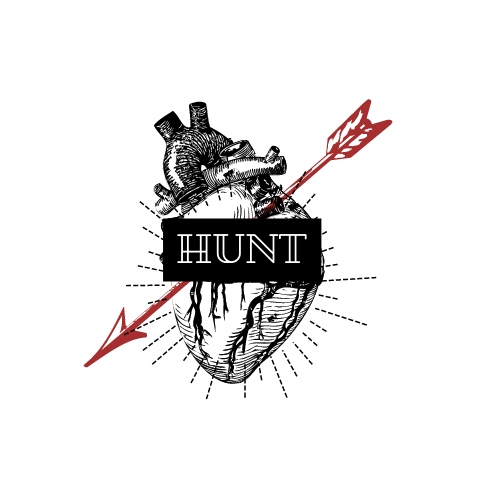10. 二人だけのブック・クラブ
Caption
ルーク・ハントと本を貸し借りする関係になった俺の執着の話。
成分表:ネームレス男主夢 | 同級生 |
「Tu me suicides, si docilement. Je te mourrai pourtant un jour」
「……なに?」
「モカシンだろう? ロベール・デスノスの」
「あー……原語だとそんな感じなんだ。これ、訳文だからさ」
木の根元に座り込んで本を読んでいたとき、突然そう話しかけてきたのがルークだった。向かいのベンチから俺が座っている木までそこそこ距離があるのに、どうして俺の読んでいる本の中身がわかったのだろうと不思議に思ったのを覚えている。
「本を交換しないか」と言い出したのも、ルークのほうだった。いつ見ても俺が必ず本を読んでいることが面白かったらしい。俺もこいつがどんな本を読むのか気になったので、とくに拒む理由はなかった。
最初に出会った林檎の木の下に交換した本を持ち寄り言葉を交わし、また次の一冊を相手に渡す。具体的な取り決めを行ったわけではなかったが、一ヵ月もすればお互いが読み進める速度は把握できた。
「また詩集? 俺、詩はよくわかんねーって言ったじゃん」
「こういうものは、思ってもみない出会いがあるのが醍醐味だとは思わないかい?」
「お前って、ファンタジーとか読んだりするの? おとぎ話とか」
「ああ、もちろん!」
「例えば?」
「動物農場」
「違うんだよなあ……いや、間違ってはないんだけどさ」
詩はよくわからないという言葉に、嘘はなかった。さらに付け足すなら、俺はルークの口を通して語られる詩が苦手だった。あの伸びやかな声で紡がれると、それまでよくわからない言葉の羅列だったものが急に鮮やかに色づき、生々しい「生きた言葉」になってしまうように感じるからだ。もちろんそんな俺の一方的な思い込みのような理由を口に出すわけにもいかず、俺は「よくわからない」と言いながらも毎回ルークの選んだ詩集を最後まで読み進めていた。
そんなある日、廊下でルークを見かけた。オクタヴィネルの背の高い生徒と談笑するその姿を見て、俺は動揺した。ルークがそれはもう楽しそうな笑顔を浮かべていたからだ。ルークはよく笑う。朗らかに、伸びやかに。「微笑み」という作品があれば、こういうイメージなのだろうなと思うほど、美しい笑顔を浮かべる。でもあんな笑顔は見たことがなかった。あんな、悪戯が成功して喜ぶ子供のような、無邪気な笑顔は。
その動揺を引きずったまま一日を過ごし、自室のベッドに倒れこんだとき。ベッドサイドにおいてある香水瓶が目に入った。
どうしてそんなことをしようと思ったのか、そのときは自分でもわかっていなかった。ルークが香水を好まないことは知っていたし、俺自身もそんなに強い香りは好きではない。でも俺は、止められなかった。明日持っていこうと思っていた文庫本をパラパラとめくりながら、そこに香りをひと噴きする手を。
次の日いつものように本を手渡すと、ルークは少し目を開いただけで特になにも言わずいつものようにニコリと笑った。昨日目にしたものとは違う、「綺麗な」笑顔。その笑顔を見て以来、俺は毎回貸し出す本にうっすらと香りをまとわせるようになった。よそゆきの笑顔が上手い、鼻のいいアイツへの嫌がらせが半分。もう半分は、この香りを嗅ぐたびに俺のことを思い出す呪いをかけるためだ。
Afterword
冒頭の詩は「お前は私のためによく死んでくれたね。私もお前のためにそうしよう」みたいな感じ。
この作品を共有

👏waveboxで拍手 💌フォームで感想
読んだよ!報告、感想とても嬉しいです!ありがとうございます!