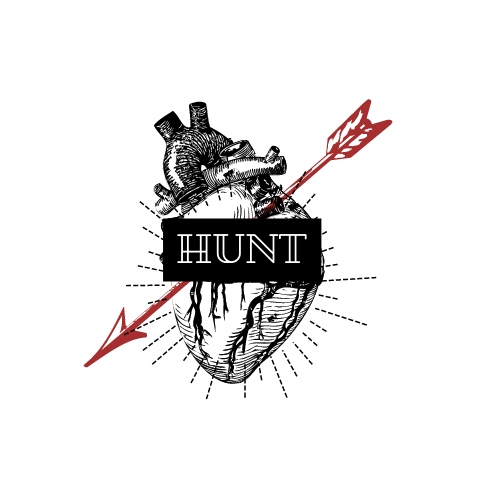2. Forrester
Caption
五歳のルーク・ハントがいとこと一緒に初めての狩りに行く話。
成分表:苗字固定いとこ夢主 | 幼少期捏造 | 流血・軽度のゴア表現あり
短編として書きはじめてから、家名がハントの家ならファーストハントはfather-son thingだろうなと途中で解釈違いになりSSになったもの。
私が生まれて初めて狩りをしたのは、五歳の誕生日のことだった。
朧げな記憶だけれど、それまでも両親は狩りについての知識は与えてくれていた。弓や猟銃、解体用のナイフなど、小さな子供には危険なものが溢れる家。私が言葉を理解し始めるよりも前から、両親は私に「それがどういう道具で、なぜ危険なのか」を説明しようとしてくれていたように思う。
地平線を真っ赤に染める、沈みゆく太陽。この草原地帯の名前の由来にもなったその美しい景色を眺めながら、彼らは私にいろいろな話をしてくれた。草原を飛ぶように駆けぬけるトムソンガゼルと、全身の筋肉を唸らせて彼らに迫りその喉元に噛みつくチーター。百万頭以上で群れを成して各地を移動する巨大なヌーたちに踏み潰されながら、川の中でその太い尾を翻し壮絶な戦いを繰り広げるワニ。シマウマたちを統率のとれた群れで追い込み捕食する、百獣の王ライオン。
ライオンのように喉笛を切り裂く鋭い爪も、ハイエナのように骨を噛み砕く頑丈な顎も、チーターのように時速百十キロで大地を駆ける強靭な脚もない。そんな人間が野生の動物たちと渡り合う唯一の方法が、道具を使った狩りだ。
だからこそ、両親が幼い私を狩りに連れて行くことはなかった。道具も使えず、自分の身体の使いかたも覚束ない子供など、野生動物の世界ではただの獲物でしかないからだ。
仲のいい親族や近隣の住民を招いて行われた私の五歳の誕生日パーティで蝋燭の火を吹き消した私に、両親は狩猟弓をプレゼントしてくれた。成長途中の私の身体の大きさにあわせて作られた、世界に一つだけの弓。
「よかったね、ルーク」
そう言って私の頭を撫でてくれたのは、私が生まれたときからよく遊んでくれていた従兄弟のライリーだった。一緒に遠乗りをしたり、弓の扱いかたや手入れの仕方を教えてもらったり。ライリーの父親が運転する車で遠くの国立公園まで出かけて、自然の中を散策したり。アーチェリーのユース選抜から声がかかるほど優秀な弓の腕前を持つライリーは、十歳以上も歳の離れた私を面倒臭がることなくいつも本当の弟のように可愛がってくれた。
そんなライリーに「はやく準備しておいで」と言われて、私の心は躍った。「本当に?ぼくも一緒に行っていいの?」と繰り返す私を見て、ライリーは笑いながら自分の狩猟弓をケースから取り出し組み立て始める。
「近くの村で小型のアンテロープが畑を襲っていると相談されてね。罠にもかからないようなんだ」
「本当は一人で行くつもりだったけど」と続けるライリーに反射的に「行く!」と叫べば、「そう言うと思った」と優しい声が返ってくる。
履きなれたトレッキングシューズの紐を固く結んで、迷彩色のジャケットに袖を通したら真新しい矢筒と弓を背負う。
「準備はできた?」
「できた!」
「小父さん、リリーを借りても?」
「勿論」
リリーというのはうちで世話をしていた馬のことだった。夕焼けの草原に存在する馬は一種類のみ。人には懐かないそれを数十年かけて品種改良し、家畜にしたのがリリーだった。
「おいで、ルーク」
太い腕に引き上げられて、ライリーに背中を預けるようにしてリリーの背中に腰をおろす。リリーは少し気難しいが、風になびく真っ黒なたてがみが美しい雌馬だった。
「行こうか」
ライリーがトンっと爪先でリリーの横腹をつつくと、動き出す景色。振り落とされないようにギュッと力をいれた僕の手を包み込むように、ライリーが手綱を握る。
人間の足では出すことのできないスピードで風を切り、私たちは野を駆けた。
十二月。乾季を迎えるこの季節は、早朝こそ十度ほどまで気温が下がるが昼間は三十度近くになる難しい季節だ。じわりと汗をかいた頬を撫でる風が心地よい。
そうして十分ほど走ったところで、おもむろにライリーが手綱を引いた。
「……聞いた話ではこの辺りを通るはずだ」
私を地面に下ろしたライリーが、リリーの耳元でなにか囁き指先で頬を優しく撫でる。それに返事をするように小さく鼻を鳴らすリリー。まるで通じ合っているかのような彼女たちのやりとりに憧れつつも、少しだけ悔しい気持ちにもなる。
開けた草原とは対照的に、鬱蒼と木々が生い茂った雨林の中を川沿いに奥へ向かって進んで行く。
熱帯雨林とサバンナ。その二つの存在が、この地域に潤沢な資源を与え生き物たちの多様性を生み出していた。国立公園のように人間の手が入ったエリアもあるが、未だ大地のほとんどは野生の動物たちの支配下にある。そこに足を踏み入れるときには、私たち人間もただの動物になるのだ。
ガサリ。
そのとき前方でなにかが蠢くのを察知し、私とライリーの視線が交差した。ライリーが小さく頷くのを確認してから、弓を構えて背中から矢を一本抜き取る。
キューイ、とライリーが鹿の鳴き声を真似た指笛を鳴らす。ガサガサと揺れる低木。そこから姿を現した生き物を見て、私たちは小さく息をのんだ。
目を爛々と輝かせた、アンテロープの一種に見える生き物。事前にたくさんの生き物の種類を学んできたはずなのに断定ができないのは、その身体が異様に大きく全身インクを被ったように真っ黒だったからだ。
なにかがおかしい。そう思った瞬間、目の前の巨大な生き物が勢いよく地面を蹴った。
「ルーク!」
その太い角を振りかぶり、こちらに向かって真っすぐ駆けてくる黒い生き物。この世のものではないようなその姿に一瞬足が怯んだ私の身体を、ライリーが強く突き飛ばした。
咄嗟に受け身をとって地面を転がった私の首根っこをつかんで、ライリーが背後の太い樹の後ろに転がるようにして身を隠す。
一体あれはなんなのか。そう問いかけようとしたとき、鼻を掠めた血のにおい。
「ライリー、」
慌てて振り返ると、そこではライリーが顔を歪めて蹲っていた。どくどくと赤黒い血が流れだすその肩から先には、そこにあるはずの右腕がない。
「落ち着いて、ルーク。止血をするからここを持っていて」
ライリーの指示に従って、布を当てた肩口をベルトでギュッと強く締めつける。
応急処置の方法は教わっていたし、父が獲物を解体するときに血抜きを手伝ったことだってある。しかし実際に目の前で血まみれになったライリーを見た私の頭に一番最初に浮かんだのは、「怖い」という感情だった。
人は簡単に死んでしまうのだと私が気がついたのは、このときだったように思う。それまでも確かに死というものを認識はしていた。しかしこのとき「ライリーが死ぬかもしれない」「失うかもしれない」と思い恐怖したことで、死という概念が私にとってぐっと近いものになった。
「ルーク、よく聞いて。アレは多分、キミの弓では通らない」
少し離れた場所から聞こえる、バリバリとなにかが砕かれるような音。
息を潜めて僕の耳元で囁きながら、ライリーが足元に落ちていた自分の弓を拾いあげる。
「私が支えるから、力いっぱい引くんだ」
「でも……」
「悪いがこうして座っているだけで精一杯でね。魔法に集中できそうにないんだ」
血を流しすぎたのだろう、いつもより青白い唇が震えている。
「やれるね?」
「……はい」
私の返事を聞き、歯を食いしばりながら笑みを浮かべたライリーの額から汗が滴り落ちた。私たちに残された時間は少なく、おそらくチャンスは一度きり。
ライリーの懐に潜り込むようにして背中を預け、ライリーの左手が構えた大きな弓に矢をつがえる。
ガサリ。
質量のあるものが地面を踏みしめる音。木の陰からそっと顔を覗かせると、巨大な生き物が角の生えた頭をもたげた。黒い毛で覆われた太い前足が地面を掻き、その口元はべっとりこべりついた液体でぬらぬらと光っている。
呼吸を整えて、両手でギリギリと弓を振り絞る。背後でライリーがぐっと息を詰めるのがわかったが、その身体がよろめくことはない。
そのとき、獰猛な光を孕んだ獣の赤い瞳が私たちを見た。
「……今だ」
矢から手を離した反動で尻餅をつきながら、空気を裂いて真っすぐ飛んでいく白い羽根を見つめる。
私を睨む赤い瞳と、その眉間に深々と突き刺さる矢。獣の頭蓋骨が砕ける音と、この世のものとは思えないような断末魔の叫び。そしてドサリと大きな身体が倒れる音。
不思議と目の前で起こる全てがスローモーションのように見えていた。
「……あとから聞いた話によると、近くの村で飼われていた小型のアンテロープが逃げ出していたそうなんだ」
「それって……」
「私の生まれ故郷では、今でも魔法とは別に黒魔術の文化が強く根付いていてね」
「じゃあソイツのせいでそのライリーさんは……」
「……ああ」
目を大きく見開いて私の話に聞き入るエペルとエース。その隣のデュースに至っては、片手で口元を覆ったまま微動だにしない。
そのとき聞こえた、コツコツと石造りの床を鳴らすハイヒールの音。
「勝手に人を故人にするものじゃないよ、ルーク」
呆れたような表情を浮かべて声をかけてきたのは、魔法生物学の担当教員であるフォレスターだった。
「フォレスター先生!?」
「キミたち一年か? なら見せたことがなかったかな」
帽子をかぶった私の頭をトン、と軽く叩いた彼女が、おもむろに白衣を脱いだ。
シンプルな半袖の下から覗く、美しい模様が彫り込まれたカーボン製の義手。
「ルーク、あんまり後輩をからかうんじゃないよ」
ライリー・フォレスター。これは私が魔法生物学の担当教員であり私のいとこでもある彼女と、生まれて初めて狩りをしたときの話だ。
この作品を共有

👏waveboxで拍手 💌フォームで感想
読んだよ!報告、感想とても嬉しいです!ありがとうございます!