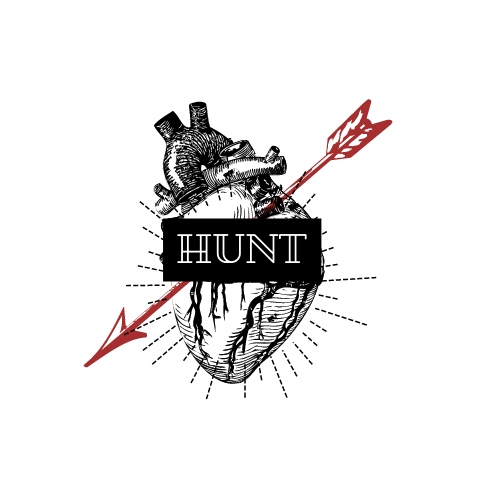4. Happy Halloween
Caption
ハロウィンの夜、付きあっていた男を殺してしまった私が、アパートの隣人であるルーク・ハントと死体を処理しに行く話。
成分表:ネームレス女主夢 | 卒業後 | 殺人・死体遺棄
アリバイ作りと死体の隠蔽方法は「How to get away from murder」が元ネタ。
しんと静まり返った、薄暗いアパートメントの部屋。窓の外では酔っ払いたちの笑い声や、騒々しい爆竹の音が響いている。
ズキズキと頭が痛むのは、飲み慣れないワインだけのせいではないだろう。ぼんやりと床に座り込んだまま、昨日掃除したばかりの木張りの床の上に広がる重さの違う二種類の赤い液体を見つめる。
ぽたり、とテーブルから雫が落ちる。それは床の上の水溜まりの表面に波紋を生み出し、暗い鏡面に映り込んだキャンドルと私の姿を歪に揺らした。
安っぽい生地で作られた丈の短いワンピースに、腰まで伸びたフード付きのマント。Little Red Riding Hoodの名前にふさわしい赤い生地には、点々と赤黒い染みが広がっている。
赤い大海原の中心に横たわる、さっきまで人間だったもの。ぴったりと身体に張りつく馬鹿馬鹿しい色のヒーロースーツは、やっぱり彼には似合っていない。
コンコン
そのとき聞こえた、誰かが玄関の分厚いドアをノックする音。
疲れ切った頭にやけにクリアに響いたその音に引き寄せられるように、私はふらふらと玄関に向かって歩みを進める。
ハロウィンの夜とはいえ、こんな時間に一体誰が。今日は彼以外誰とも約束していないし、追加のピザを頼んだ覚えもない。
身体は血まみれで、床には死体。このドアを開けるべきではないということなんて、考えなくてもわかる。冷静にそう考える頭とは裏腹に、私の身体はまるでそうすることが正しいかのように迷いなくチェーンを外すと、金属製の取っ手を握って重いドアを開いた。
「Bonsoir……おや、お取込み中だったかな?」
階段の踊り場のぼんやりとした明かりに照らされた、金色の髪。チカチカと輝く切れかけの蛍光灯が眩しくて目を細めながら、私より頭ひとつぶん背の高い男と視線をあわせる。
「こんばんは、ルーク。どうしたの?」
「美味しいシャンパーニュを手に入れてね。一人で飲むよりキミを誘ったほうがいいかなと思って」
そう言いながらちらりと私の背後に目をやった彼は、キュッと口角を上げて微笑むと「というのは建前で、大きな音が聞こえたから気になったんだ」と言葉を続けた。
「お邪魔しても?」
朗らかな声と、私をまっすぐ射抜く美しいエメラルドの瞳。質問の形をとっているだけで、最初から私に断るという選択肢は与えられていないように思えた。
先に目を逸らしたのは、私のほうだった。言い訳をするように「散らかってるけど」と呟きながら隣の部屋の住人を招き入れ、妙に楽しそうな「Laisse tomber!」という返事を聞きながら死体の転がる部屋へと歩みを進める。
「これはこれは」
「……散らかってるって言ったでしょ」
真っ赤な水溜まりの中心に沈む、冷たくなった男の身体。テーブルの上にワインボトルを置いて、ルークが死体の前でしゃがみこむ。
目の前で人間が一人死んでいるというのに、顔色ひとつ変えずに死体を観察するルーク。大理石の彫刻のようなその横顔を眺めながら、これからどうすればいいんだろうなと他人事のように思う。
「手を洗ったほうがいい。衣装にはよくあっているが、衛生的ではないからね」
そう言いながら、ルークに連れられてキッチンへと向かう。言われるがままシンクで手を洗えば、赤く染まった水が流れた。
「痛むかい?」
「えっ?」
「顔。殴られたんだろう。唇が切れてしまっているよ」
水で濡らしたハンカチをそっと口元に当てられて、初めてそこが鈍い痛みを持っていることに気がついた。
そうだ、殴られたんだ。いつもみたいに。出かける予定だったのに、無理やり服を脱がそうとしてくるから。だからお酒は飲みたくないって言ったのに。
この顔の傷は明らかに殴られたものだし、身体にもまだいくつか痣が残っている。
日常的に暴力を受けていた人間が、命の危険を感じて咄嗟に身を守ろうとして相手を殺してしまった。正当防衛。今すぐ自首すれば、情状酌量されるかもしれない。でもお酒を飲んでしまったから、警察署まではルークに運転してもらわないと。
記憶と一緒に浮かび上がってくる、「これから」のこと。ついさっき人を一人殺したとは思えないほど、私の心は凪いでいた。
「ルーク、」
「コインで決めようか」
「……なにを?」
「私たちの運命を」
「私たち?」
不思議な物言いをする。彼を殺したのはまぎれもなく私で、これは私の問題なのに。二人がけのソファーがぐっと沈んで、革の手袋に包まれた指先が器用に銀色のコインを踊らせる。
「表が出たら、私はキミを警察署まで連れて行こう」
「……裏が出たら?」
「一緒にコレを処理しにいこう」
一体何を言っているのか。そんな思いを込めてルークの顔を見上げると、彼はいつもと同じように穏やかな笑みを浮かべてこちらを見つめていた。
「……どうして?」
「今日はハロウィンだからね」
全く説明になっていないのに、その答えは不思議と私の胸にすとんと落ちた。
「わかった」
「C'est bon」
嬉しそうにすうっと目を細め、ルークが指先でピン、とコインを弾いた。くるくると宙を舞う、小さな銀色。コインごと手の甲を覆ったルークの右手を固唾をのんで見つめる。
「……裏だ」
情けないことに、顔の描かれたコインの裏側を目にした私は静かに安堵していた。交流はあるがお互い相手のことを深くは知らない、どこかミステリアスな隣人。そんな得体のしれない相手を共犯者として迎えることになったのにも関わらず、だ。
「このラグ、一緒に処分してもいいかな?」
「あー……いいよ。汚れちゃったし」
わずかに血が飛び散った、地味な色のラグ。そもそも私の好みじゃなかったし、という言葉を飲み込んで立ち上がれば、ルークが死体を軽々と持ち上げてラグの上に寝かせた。
そのままくるくると死体を転がしてラグで包んでいくルークの背中を横目に、私は床の汚れを落とすためのバケツとモップを取りに行く。
床に広がった液体を拭き取ったモップをバケツに突っ込むと、バケツの中の水がじわりと濁った。
大体の汚れを拭い終わったあとも、床に残ってしまった黒い染み。バケツの水を替え、買い置きしていた酸素系の漂白剤を溶かした溶液を作っていると、ルークがじっとこちらを見ていることに気がついた。
「どうしたの?」
「失礼。手慣れているなと思って」
「……女の子だからね」
その答えを聞いたルークが少し目を丸くして「なるほど」と呟いたのがなんだか可笑しくて、思わず苦笑する。
「念のため、明日にでもワックスをかけよう」
そんなルークの声を聞きながら、またぼんやりと明日があるのかと思う。着替える時間も気力も惜しくて、バカみたいなコスチュームの上からカーキのモッズコートを羽織った。
「車を借りても?」
「うん。アパートのすぐ前に停めてあるから……先に様子を見に行ってくるね」
「Merci」
みんな出払っているのか、相変わらず騒がしい外とは対照的にアパートの中はしんと静まり返っている。部屋の前にも階下にも誰の姿も見えないことをルークに告げると、彼は穏やかに「それでは行こうか」と言いながら筒状に丸めたラグを担ぎ上げた。
幸運にも、誰ともすれ違うことなく白色のフィアットに乗り込んだ私たち。シートベルトを締めながら、バックミラー越しに後部座席に横たわるラグにちらりと視線をやる。
そのとき突然車内に響いた音楽に、私はびくりと身体を揺らした。驚いて運転席を見やると、ハンドルを握ったルークが悪戯っ子のような微笑みを浮かべている。
車外から聞こえてくる、仮装した学生たちの騒ぎ声。それをかき消すようにラジオの音量を上げるのと同時に、ルークがぐっとアクセルを踏み込んだ。
M83のMidnight City。随分と懐かしい気もするが、夜のドライブのお供には悪くない選曲だ。
学生たちが練り歩く大通りを抜け出して、ルークと二人、ラジオから流れるメロディにあわせて口ずさみながら薄暗い住宅街の中を走り抜けていく。
窓の外を流れていく、町の光。見慣れたその風景が、今日はやけにキラキラ輝いて見える。
「ミルクと砂糖は?」
「ブラックでお願いしようかな……運転席で眠るわけにはいかないからね」
灯油と黒いゴミ袋を購入するため、途中でガソリンスタンドに併設されたコンビニに立ち寄った。もちろんそれだけでは店員の印象に残ってしまうので、スナックや眠気覚ましのコーヒー、マッチとサイケな色のドーナツ。あとは下世話な店員に勧められた、レジ横のコンドーム。
そこから再び車を走らせて、ようやく目的地に到着する。近所の大学のすぐ裏手に位置する、深い森。目立たない位置に車を停め、ルークと二人で丸めたラグを担いで森の中へと分け入っていく。
二人でと言っても、私はほとんど手を添えているだけのような状態で、実質的にはルークが一人で自分よりひと回りは大きな死体を担いでいた。木々が鬱蒼と生い茂り、月の光すら入ってこない森の中を奥へ奥へと進んで行くその足取りは、成人男性の身体を担いでいるとは思えないほどしっかりしている。
静まりかえった夜の森の中に響く、二人分の息遣いと落ち葉を踏みしめる音。そのまましばらく歩き続けて低木の少ない場所に出たところで、ルークがドサリと丸めたラグを地面に下ろした。
「……ここまで来れば、煙も目立たないはずだよ」
その言葉を聞いて、ラグの端から端までまんべんなく灯油を振りかけていく。
死体を燃やそうというのは、ルークの提案だった。死体を埋めるのは労力のわりに証拠が残りやすい。それならば燃やしてから細かく分けて、ゴミに出したほうがいい。車内で「埋めるの?」と尋ねた私に、彼はそう教えてくれた。
「別れは告げた?」
「……もうずっと前に」
「……そう」
大量の灯油が染みこんだラグに向かって、放物線を描いて飛んでいく火のついたマッチ。次の瞬間、目の前で熱がボッと爆ぜて、私たち二人の顔を明るく照らした。
パチパチと音をたてて燃える、人間だったもの。恋人というラベルの下で私を押さえつけ蹂躙した男が、ただのものになっていく。
人間を殺し、その死体を燃やしているというのに、私はここ数か月で一番晴れ晴れとした気持ちだった。
私はとっくの昔に彼のことを嫌いになっていて、そんな相手に別れを告げることができない自分のことも嫌いになり始めていたんだと思う。
「綺麗だね」
「Beaute」
隣に並んだまま、お互いひとりごとのようにそう呟く。火は魔物だ。そんな言葉を思い出しながら、私はただ静かに燃え盛る炎を見つめた。
寒空の下、身を寄せ合うようにして炎を眺めたあと、私たちは真っ黒な燃え残りを木の枝でバラしてゴミ袋にしまった。
あわせて三つのゴミ袋に変わった、私の恋人。随分と小さくなったそれを後部座席に乗せて、私たちは再び車に乗り込んだ。
町まで戻る前に、私たちは森の隣にある大学のキャンパスに向かった。天高く立ち上る炎。ハロウィンを祝う巨大なBon Fireの前で、浮かれた大学生たちに混ざって自撮りをする。
私とルークがこの時間ここにいたことを証明するその写真をマジカメに載せ、私たちはまた夜の街を駆け抜けた。
ゴミ袋は、路地裏に設置されたごみ用のコンテナを何か所か巡って捨てた。ハロウィン翌日の収集日。いつも以上にゴミが増えるその日に、紛れ込んだ焼死体に気づく人はいないだろう。
ラジオから流れてくるボウイのHeroesにあわせて歌いながら、私たちは日常の待つ町へ帰ってきた。
少しだけ漂白剤のにおいのする部屋のドアを開け、ルークの持ってきたシャンパンの栓を抜く。
「……別れと、新しい日常に」
「Sante!」
グラスを掲げ、美しい金色の液体を一気に煽る。喉の奥で弾ける細やかな泡。グラス越しに私を見つめる、エメラルドの瞳。その蠱惑的な輝きに吸い寄せられるように、グラスから手を離す。
「日常」が音をたてて壊れていくのを感じながら、私はゆっくりと目を閉じた。
この作品を共有

👏waveboxで拍手 💌フォームで感想
読んだよ!報告、感想とても嬉しいです!ありがとうございます!