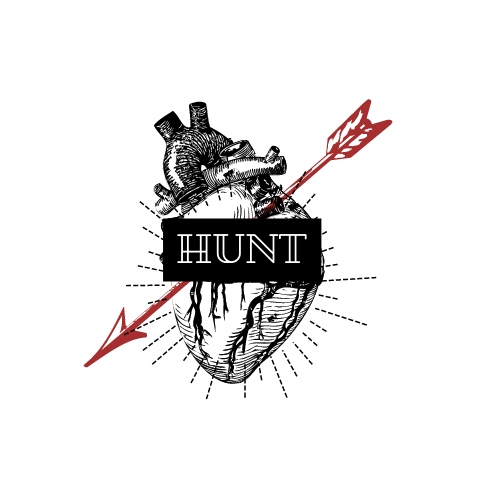5. The Night We Met
Caption
学生時代にプロムに出席できなかった僕がルーク・ハントと一緒にプロムをやり直す話。
成分表:男主人公 | 恋人 | 女装
薄汚れたカーペットの上に座り込んで、そういえばあの日も僕はこうして部屋の隅でうずくまって泣いていたなと唐突に思い出す。
満天の星空が美しい夜だった。閑静な住宅街。家の前の道がいつもより少し騒がしいのは、思い思いにドレスアップした少年少女がパーティ会場を目指して歩いていくからだ。楽しそうに笑いあいながら道を行く、春の訪れを祝う精霊たちのように華やかな彼ら。その後ろを、同じように着飾った同級生たちを乗せた車が流行りのポップミュージックを大音量で流しながら通り過ぎていく。
四年にわたる学生生活の終わりを祝う、プロムの夜。夜空で輝く星のようにきらめく彼らを、僕は薄暗い部屋の小さな窓から眺めていた。
ハイスクールでの生活は、楽しいものだった。自分と向き合い、これからどう生きたいのかという指針を定めることができたし、決して多くはないが生涯にわたって付きあえる友人にも出会うことができた。それになにより、学校にいる間はあの時陰鬱とした家にいなくて済んだ。
兄が死んだあの日から、僕の家の中に流れる時は止まってしまった。優しく聡明でいつも人の中心にいる、誰からも愛されるような魅力にあふれた人。少し年の離れた僕があとをついてまわっても面倒臭がることなく全力で一緒に遊んでくれる兄のことが、僕は大好きだった。
元々週末には教会に通い、食事をする前には必ず家族でそろってテーブルにつき祈りを捧げるような家庭だった。しかし兄を喪ったその日から、両親の「信仰」は目に見えて加速した。
数ある戒律の中で最も両親が重視したのが、貞節と節制。兄が死んだのが、年上の恋人とのデートの最中だったからだろう。もしくはそれまで口に出していなかっただけで、息子が二人そろってゲイに生まれたことを認めたくなかったのかもしれない。
家の中で、僕に自由はなかった。友達を家に呼ぶことも、彼らとどこかに出かけることも禁じられ、学校と教会に出かける以外はずっと家の中で過ごすように言われた。
唯一の救いは、急につきあいが悪くなった僕と変わらず接してくれた友人たちがいたことだ。四年になってしばらく経ったある日、突然流行とは程遠い地味でダサいシャツのボタンを一番上まできっちりと閉め、短く切った髪を撫でつけて登校した僕。友人たちはそんな僕の見て笑うことすらせず、心配そうに「なにがあった?」と尋ねた。
そんな風に親の監視の目がない学校内で過ごす時間だけを心の支えに生き延びて迎えた、学生生活最後の日。
普通に遊びに行くことすら禁止されていた僕にプロムへの参加が許されるはずもなく、僕は自室として与えられていた小さな部屋の窓から道行く同級生たちを見下ろし静かに泣いた。
「僕さ、プロムでドレスが着たかったんだ」
フォルダに溜まった未読メールをチェックしながら、独り言のようにそう呟く。
全てを捨てて地元を離れて十数年。あの頃好きな格好ができなかったフラストレーションを昇華するように服飾の道に足を踏み入れた僕は、企業でしばらくデザイナーとして働いたあと自分のブランドを立ち上げた。
「その頃から服作りを?」
「まさか。でも頭の中ではデザインしてた。こういう素材で、こういう形のドレスがいいなって」
ココアの入ったマグカップを受けとって「Merci」と微笑めば、隣から「De rien」と朗らかな声が返ってきて頬が緩む。
仕事相手を通じて知り合ったこのルーク・ハントという男と付き合い始めて、もう五年になる。最初にルークと顔をあわせたときに僕が抱いた感想は「変わった奴もいるもんだ」だった。そんな相手とデートを重ね、ついにはともにひとつ屋根の下で暮らすことになるなんて、一体誰が想像しただろう。
ルークの好きなものや嫌いなもの、考え事をしているときに出る癖から今日の下着の色まで。この五年間で彼に関する知識は増える一方だが、相変わらずつかみどころのない不思議な人間だと思っている。まあ、ルークのそんな部分を好ましく思っているのだから、世間一般的に言えば僕も変わった奴なのかもしれない。
「なるほど……ではやり直そう」
「やり直すって、なにを?」
「なにって、決まってるじゃないか! プロムだよ」
キョトン、とした顔でそう言われ、今度は僕が鏡写しのような表情を浮かべてしまう。
「さあ、出かけようか」
「……ちょっと待って、今から?」
「Oui!」
にっこり笑ってそう答え、どこかに電話をかけ始めたルークに手を引かれ、僕は着の身着のままで自宅を飛び出した。
Dua LipaのPhysicalで幕を開けるお気に入りのプレイリストを聴きながら夜の道路を駆け抜け、ルークは馴染みのサロンの前で車を停めた。
ショーやルックブックの撮影用のヘアメイクだけではなく、僕自身も個人的に世話になっている美容師が営むそのヘアサロン。普段ならとっくに営業を終えている時間であるのにもかかわらず、店内には煌々と明かりが灯っている。
「いらっしゃい」
「ごめん、オフの時間に。ルークに頼まれたんだよね?僕もよくわかんないまま連れてこられて……」
「野暮なことは気にしないで、アンタは黙って座ってればいいの」
子供の頃の嫌な思い出を上書きするように、肩まで伸ばした黒い髪。軽くシャンプーをされたあと「傷んでる部分ちょっと切るね」という声とともに聞こえてきたハサミの音に耳を澄ませる。
「できたよ」
「……ん、ごめん、ちょっと寝てた」
「締め切り近いのは知ってるけど、ちゃんと睡眠とりなよ?」
「うん、ありがと……わ、可愛い~!」
「当たり前でしょ。アタシがやったんだから」
髪に触れる優しい手つきと心地よいハサミの音によって、いつのまにか眠りの世界にいざなわれていたらしい。欠伸をしながら目の前の鏡に目をやった僕は、そこに映る自分の姿を見て思わず身を乗り出した。
80年代の女優のように大きく巻かれた僕の髪。痛んだ部分を取り除き、丁寧にトリートメントされたそれは自分の髪とは思えないほど艶やかで、思わず見とれてしまう。
完全にすっぴんだった目元はスモーキーなアイシャドウで美しく彩られ、瞬きするたびにアクセントに引かれたシルバーのアイラインがキラキラ輝く。口元には真っ赤なリップ。少しだけオーバーリップ気味に引かれたそれは、僕の唇にぽってりとした色気を与えていた。
「Beaute!」
そんな声で顔を上げると、鏡越しに僕を見つめるルークと目があった。
「さあ、次はこれに着替えて」
何故か僕よりも楽しそうなルークを見て笑いながら、手渡された衣装袋を開いて驚いた。
深みのあるバーガンディーが美しい、シルクオーガンジーのドレス。背中が大きく開いたスレンダーラインのそれは、デザイン画からそのまま飛び出してきたのかと思うほど、僕が子供の頃に夢見て描いたドレスそのものだった。
「な、んで……」
「この間資料探しを頼まれただろう?そのときに見つけてね」
そう言うルークの手に握られていたのは、下手糞なデザイン画。子供が描いた落書きにしか見えないその横に書かれた「目指せプロムクイーン!」の文字を見て、僕の目からぽろりと涙が零れた。
「ああ、泣き顔も美しいけれど、折角の化粧が崩れてしまうよ」
「だって、」
「Mon cheri、早く着て見せてくれないかい? これを身に纏ったキミの姿を想像しながら、今日まで秘密を漏らさないよう我慢してきたんだ」
そう言って、ルークが僕の頬にそっとキスを落とす。子供をあやすようなその優しい口づけが嬉しいやら可笑しいやら。僕は泣き笑いをして顔も心もぐちゃぐちゃにしたまま、ドレスを抱えて更衣室へと向かった。
どうしても女性よりゴツゴツとした印象を与える肩を隠すように、胸元から上はレース地で覆い、そのぶん背中には大胆な切込みを。スレンダーラインにしたのは、ある程度ボディラインのカバーをしながら同時に背の高さを生かしたかったから。
デザイン的な甘さはあるが、その部分も含めて確かにこれは僕が生まれて初めてデザインした、あの夜着ることができなかったドレスだった。
おそるおそるドレスに袖を通してみれば、それは怖いくらい今の僕の身体にぴったりフィットする。ドキドキしながら鏡に全身を映してみて、僕はまたぽろぽろと涙を零した。
あの頃より随分と背が伸びて歳をとったけれど、鏡の中にはプロムクイーンを夢見る赤いドレス姿の少年が映っていたから。
ドレスと一緒に手渡されたシルバーのハイヒールを履いて隣の部屋へ戻ると、そこでは黒いタキシードに着替えたルークが待っていた。
「……Comme c'est beau!」
「……Toi aussi」
職業柄フォーマルな服装をすることには慣れているし、ドレスを着るのも初めてではない。しかし今日は妙にドキドキしてしまい、まともにルークの顔を見ることすらできない。
「おっと、忘れるところだった」
そう言いながらルークがとりだした、小さな箱。ふたを開けると、そこには白い花をあしらった飾りが二つ並んでいた。
プロムコサージュと、ブートニア。ドレスと同じ深い赤色の薔薇を中心としたその小さな花束をルークの胸元に差してやれば、今度はルークが僕の手首にその美しい飾りをつけてくれる。
「On y va ?」
「Oui!」
恭しく差し出された腕をとり、オーナーに礼を言ってからサロンをあとにする。再び車に乗り込み夜の街を駆け抜ければ、冷たい夜風が僕の頬を撫でた。
ルークが再び車を停めたのは、街から少し離れた高台にある小さな公園の側だった。
街全体を見渡すことができるこの場所は、僕たちが初めてのデートの夜に訪れた思い出の場所でもある。……まああのとき僕は完全に酔い潰れてここでゲロを吐くだけの肉塊になっていたから、実際はよく覚えていないんだけど。
「On danse?」
「Bien sur」
僕の返事を聞いてにっこり笑ったルークがスマホに触れると、カーステレオから柔らかなギターの旋律とともに美しいコーラスが流れ出す。The night we met. 星空の下で寄り添うように抱き合って、僕たちは流れる音楽にただ身を任せて踊った。
Afterword
この作品を共有

👏waveboxで拍手 💌フォームで感想
読んだよ!報告、感想とても嬉しいです!ありがとうございます!