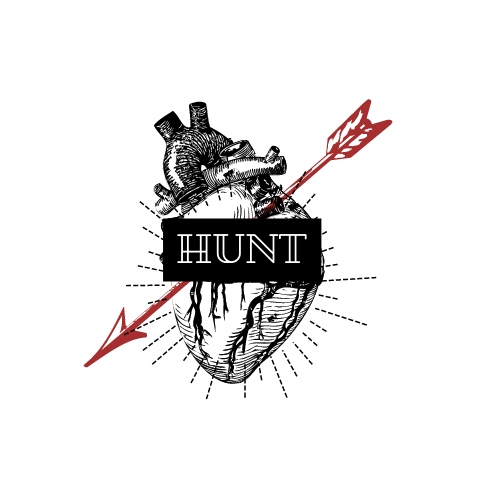14. Hare and Hounds
Caption
Twitterで呟いていた「ルーク・ハントともう一週間口を聞いていない理由を問われたウサギの獣人の僕、「ヤッてる最中に片手で両耳を掴まれたからだよ」と言うと「なんだそんなことで」「痴話喧嘩じゃん」と言われたので「人間にとっては”そんなこと”なんだろうね。でもこれは僕たちの尊厳に関わる問題だから」って静かに言う」話。
成分表:ネームレス男主夢 | ルーク・ハント不在 | 恋人 | 喧嘩
「先輩たち、」
まだ喧嘩してるんですか? と呆れたように尋ねられ、オレは咀嚼していたレタスを飲みこみフォークを置いた。ランチタイムで賑わう大食堂。軽く二人前はあるのではないかと思われる料理をペロリと完食してから、さらに山盛りのチップスを分けあいはじめた同じ部活の後輩たち――ジャック・ハウルとデュース・スペード――を交互に見やり、ため息を吐く。
「……してるよ」
「もう一週間は続いてません?」
「そうだな」
「その……そもそもなんで喧嘩になったんですか?」
「あの飄々とした人相手に喧嘩になるんですか?」
ずっと気になっていたのを我慢していたのか、次から次へと質問が飛んでくるので苦笑する。そんなに他人の喧嘩が気になるものかと不思議に思ったが、ほとんど毎日顔をあわせていた相手と突然目もあわせなくなったのだ。気にするなというほうが無理な話だろう。それに、個人的な問題で他人に当たり散らすほど子供ではないとはいえ、周りに気を遣わせてしまっている自覚はある。
「こないだルークとヤってたときにさ」
一瞬の間をおいて気まずそうに目を逸らしながらチップスをつまむ手を止めた二人に、「お前らが聞きたいって言ったんだろ」と釘を刺してから話を続ける。
「アイツ、オレの耳を掴んだんだよね。片手でこうやって、両耳まとめて」
頭上に手を伸ばし、ジェスチャーで再現してみせれば、ジャックが露骨に顔を歪めた。対称的に、その隣でキョトンとした表情を浮かべるデュース。
「デュースさ」
「えっ? はい!」
「いま「それだけのことで」って思ったでしょ」
「……はい」
少し迷ったあと、デュースがまっすぐオレの目を見つめて頷いた。下手にごまかしたり嘘をついたりはしない。少し不器用でまっすぐすぎるきらいはあるが、オレはデュースのこういうところを好ましく思っている。だから怒らず話を続ける。知らないことは罪ではないし、オレたちは学ぶためにここにいるから。
「そろそろ魔法史でもやると思うんだけど」
そう前置きして、小さく息を吸ってから口を開く。
「1933年、新聞に一枚の写真が載ったんだ」
まだ世界が今のようには「ひとつ」になっていなかったあの頃。
「人間が、「狩った」ウサギの獣人の耳を掴んで記念撮影した写真だよ」
獣人が多く暮らすエリアではプライマリースクールで習うこと。今でも初めてあの写真を目にしたときの衝撃は覚えているし、きっと生涯忘れることはないだろう。あの日オレは自分がウサギの獣人に生まれたことに絶望したし、初めて世界に恐怖を感じた。もちろん、そういう経験はなにもウサギの獣人に限ったことではない。魔法薬の材料にできるからと生きたまま羽根をもがれた妖精族や、食べると不老不死の力を得ることができるという迷信のために釣り上げられた人魚族。己の力を示すために狩られたライオンの獣人もいたし、なにより人間族のあいだでも「他とは違う」ことを理由にたくさんの命が失われてきた。愚かで悲しい、しかし無かったことにすることはできない命の歴史。
「ルークはよくも悪くも狩人なんだよ」
あのときのアイツの行動に他意がなかったのは分かっている。ルークは確かにろくでもない人間だが、馬鹿ではないからだ。オレたちがただの同級生だった頃も、その隣に「恋人」というラベルが追加されてからも、アイツにとってオレは「ウサギの獣人」だ。アイツのアイデンティティが「人間」であることよりも「狩人」であることに依存している以上、それはこれから先も変わることがないだろう。その点についてはオレも納得したうえで一緒にいるし、そういうところを気に入ってすらいる。
「だからこそ許せねえの」
オレの耳をつかむということがどういうことなのかよくわかっているはずのルーク狩人が、はずみでとはいえあんな行動をとったから。すごくムカついたし、怖かった。あの一瞬、オレは確かに恐怖したんだ。目の前の人間に。
どれだけ気心が知れた相手でも、仲がよくてもダメなんだ。これはオレたちの尊厳に関わることだから。
「……すみません、俺、なにも知らずに……」
「いーよ、オレも人間のこと全部知ってるわけじゃねえし」
眉間に皴を寄せて項垂れたデュースの頭をわしわしと撫でてやる。本当に可愛い後輩たちだ。
「それであの人が謝らずこんな長期戦に……?」
「そんな……許せねえ」
すると一転して、デュースがハッとなにかに気づいたように固く拳を握り締め、それに呼応したジャックと二人して席を立とうとしたので、慌てて静止の声をかける。
「いや、ルークはすぐに謝ってくれたし、オレももう怒ってはねえんだけど……耳つかまれたときに咄嗟に蹴りいれちゃってさあ」
わりと本気で蹴ったから、アイツの肋骨何本か折っちゃったんだよね。それ以来顔あわせんのが気まずくて。あまりの恥ずかしさに口元に手を当ててもごもごとそう言えば、オレをポカンと見つめていた二対の目がキラキラ輝きはじめる。
「折ったんですか?あのハント先輩の骨を!?」
「やっぱり先輩すげーッス!」
「いやお前ら声がでけえしダメだからな暴力は……」
やっぱり話すんじゃなかったか、と後悔しはじめたそのとき。オレの耳がぴくりと動いた。
「悪い、オレ行くわ」
「えっ、まだ昼休みは……」
「あー……その、ルークに呼ばれたから」
長い耳を揺らしてそう言えば、二人が納得したように「ああ」と呟く。
「それにお前らに話してちょっとスッキリしたし、そろそろ向きあうよ」
まあ穏便に済むかどうかはわからねえけど。心の中でそう付け足しながら、席を立つ。目指すは中庭。仲直りの時間だ。
この作品を共有

👏waveboxで拍手 💌フォームで感想
読んだよ!報告、感想とても嬉しいです!ありがとうございます!