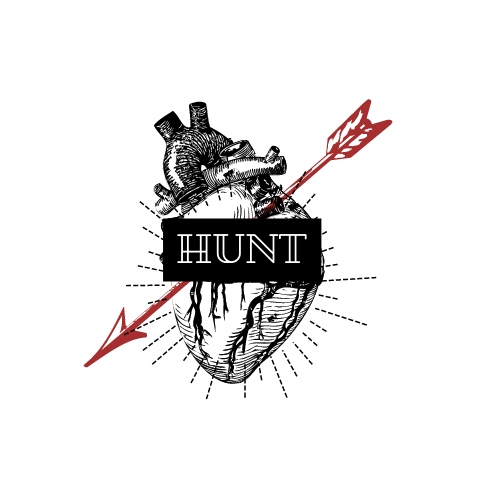15. ネロリの手袋
Caption
Twitterで呟いていた「ホリデーに帰りたくない家に帰って実家の古びた安宿を手伝いながら殴られて痛む身体を小さく丸めてルーク・ハントにもらった手袋を握り締めて眠る静かな夜」の話。
成分表:ネームレス男主夢 | 同じ寮の後輩 | 児童虐待
小さなベッドとワードローブ、それと足が一本欠けた古いテーブル。それが僕の全ての持ち物で、その三つだけでいっぱいになってしまうほど小さな屋根裏部屋が僕に与えられた唯一の居場所だった。
階下から聞こえる賑やかな音楽と、酔っ払いたちの笑い声。時刻はもう午前三時を迎えようとしているのにも関わらず、その喧噪はとどまるところを知らない。このバカ騒ぎはなにも昨日や今日はじまったことではなく、僕が生まれる前からずっと続いてきたものだ。そして僕は明日も安酒と料理の脂、そして煙草の煙で汚れた酒場の掃除をするため朝六時には目を覚まし階下に向かわなければならない。それが、「役に立たないただのガキ」である僕がこの家に置いてもらうために満たさなければならない条件だからだ。
暖房のない部屋の中、薄っぺらいブランケットを身体に巻きつけベッドの上に横たわる。少しでも熱を逃さないために身体を小さく丸めると、さっき殴られたばかりの脇腹がズキズキと痛んだ。痛くて、寒くて、どうしようもなく寂しい。久しく忘れていた、僕の日常。早く寝ないとまた朝が辛くなる。そんなことは嫌というほどわかっているのに、どんどん気持ちが落ち込んで目が冴えてくる。
だから僕はベッドサイドに置いたカバンの中から茶色い鹿革の手袋を取り出し、抱き締めた。その滑らかな生地に鼻先を埋めれば、ふわりと香る獣のにおいとネロリの香水。心臓の奥のあたりで渦巻く薄暗いもやを少しずつほどいてくれるその手袋は、憧れの人にもらった僕の宝物だった。
ナイトレイブンカレッジに入学するまで、僕の世界はこの小さな屋根裏部屋と、階下にある掃き溜めのような酒場の二つだけで構成されていた。酒場のお客さんが口添えしてくれたお陰で学校には通わせてもらっていたけれど、あの頃の僕はあまりいい生徒ではなかったように思う。家に帰ってから夜中まで酒場を手伝って、また早朝から片づけをする毎日。宿題をやっていく時間などなく、授業中に居眠りをしてしまうことも多かった。
だからあのナイトレイブンカレッジから入学許可証が届いたとき、僕は本当に驚いたんだ。確かに僕は物心つく頃には魔法を使えていたけれど、自分が魔法士になるなんて想像すらしたことがなかったから。両親は魔法が使えない人間だし、そもそもハイスクールを退学になったほど筋金入りの勉強嫌いだ。そんな彼らを説得するのは大変だったけれど、最終的に学費がかからないことが進学の決め手になった。僕が寮生活を送っている間、彼らは労働力を一人分失うことになる。だから生活費や学園生活に必要なお金を支援することはないし、むしろお前が仕送りをしてくるべきだ。両親の話を要約するとこうだ。今まで実家での労働に対して一度も対価をもらったことなどなかったが、僕はその無茶苦茶な条件をのんで馬車に乗った。あの酒とたばこと脂の臭いが染みついた場所から逃げ出したかったし、死ぬ前にこの目で知らない世界を見てみたかったから。
意外にも、学園生活は楽しかった。名門校というからてっきり金持ちばかりが通っているものだと思っていたが、僕のように経済的に問題を抱えた生徒も少なくはない。だから僕は校内でのアルバイト中に出会ったラギーという生徒と二人で、僕たちのような生徒のためのネットワークを構築することにした。コネクションも金もない生徒たちが、もっと簡単に中古の制服や教科書を手に入れられるように。取り分は50-50。情報収集や根回しはラギーの仕事で、表立った対応や事務的な手続きは僕が担当することで合意した。
「いい金持ち」であるためには、様々な義務が発生する。そのうちの一つが僕たちのような人間を援助し、社会をよくしていくこと。Noblesse oblige. まあ名前なんてどうでもいい。大切なのは、なにを得られるか。幸い僕は人と話すことが苦ではなかったし、相手が求めているだろう「同情したくなるような貧乏人」を演じることも得意だった。
そんな風に立ち上げた事業を運営しながら単発のアルバイトをこなし、授業を受け、予習復習の時間も確保する。毎日目が回るほど忙しかったが、楽しかった。理不尽に怒鳴られたり、殴られたりすることがなく、自分の裁量で時間が使える。そのうえ働けば働くほどお金がもらえるのだ。これが自由。生まれて初めて、生きることを楽しいと思った。
もちろん悪意を向けてくる奴らも存在したが、まともに喧嘩もしたことがないボンボンなんて怖くもない。ビール瓶で殴られたことのない奴らの思う「嫌がらせ」なんてたかが知れているし、ちょっと痛い目にあわせればすぐにちょっかいをかけてくることはなくなった。
そしてそんな奴らを「ちょっと痛い目」にあわせていたときに出会ったのが、ルークさんだった。地面に落としてしまった僕の腕時計を踏みつけ「ああ、すまない。君の時計だったのか。ガラクタかと思った」と笑った上級生。そんな彼に拳にはめた腕時計を使って「時計の良し悪しは丈夫さで決まるんですよ」と教えてあげたあと、時計についた血を拭いながら振り返った先に、木にもたれてじっとこちらを見つめるルークさんがいた。
「……魔法は使っていません」
「そのようだね」
「罰則対象ですか?」
「そうかもしれない」
そんなことより、迷いのない良い拳だったね。と赤くなった手の甲を撫でられて、僕は取り繕うことも忘れてぽかんと目の前の人間を見つめた。
ルークさんは、変わった人だった。見た目や振る舞いは間違いなく上流階級の人間のそれなのに、彼はあまりにも本能的で自由だったから。
幼い頃から大人たちに囲まれて育ってきたお陰で、人の腹の内を探るのは得意なほうだった。しかしルークさんに関して言えば、僕はなにもわからなかったし今でもわかる気がしない。それほど彼はルーク・ハントという人間を演じることが上手く、僕はそんな彼に、全てを暴かんとする美しい瞳と伸びやかに世界を彩る声を持つ狩人に、どうしようもなく憧れた。
そんな僕が、一度だけルークさんの前で弱音を吐いたことがある。期末テストを終え、学園全体がホリデー気分で浮かれる中。あの家に帰らなくてはならない憂鬱さゆえに談話室の団欒に混ざることができずにいた僕に、ルークさんが声をかけてくれたときのことだ。
「こんな気分になるなら外の世界なんて知らなきゃよかった」
冗談交じりに口にした言葉は、しかし確かに本心から零れ出たもので。慌てて「まあホリデーなんて一瞬なんで」と笑いながらつけ加えた僕をじっと見つめて、ルークさんが言った。
「私は今この場にキミがいて、共に過ごせることを嬉しく感じているよ」
静かで、穏やかな声。
「それに世界は広い。私たちが思っている以上に、ずっと」
そう言いながら視線を上げたルークさんにつられて、窓の外に広がる夜空を見上げた。冬の冷たい空気の中できらめく無数の星々。星空なんて見慣れているはずなのにやけに綺麗に見えたあのときの光景は、今でもはっきりと覚えている。
「……忘れるところだった」
しばらく黙って星空を眺めたあと、ルークさんが懐からなにかを取り出し僕の前に差し出した。
「手袋、ですか?」
「ああ。これは私が初めて仕留めた鹿を使って作らせたものなのだけれど……キミに持っていてほしいと思ってね」
「えっ、そんな大切なもの、頂けません」
それに僕、なにも用意してないですし。動揺から、声が震える。そもそもルークさんのような人に僕があげられるものなんて、なにもないのに。情けなくて顔も上げられない僕の手をとって、ルークさんが手袋をはめてくれる。
「なんてことはない、日頃のお礼だよ。それに私の手には少し小さくなってしまって」
「……ありがとうございます!大事に、します」
僕の手をぴったり包み込む、柔らかくなるまで使い込まれた温かな革。嬉しさに緩む顔を隠すように両手で口元を覆えば、革のにおいに紛れて爽やかなオレンジの香りがした。1㎏のビターオレンジの花からわずか1gしか精製できない、極めて希少な精油。その香りを纏わせた手袋のことを「ネロリの手袋」と呼ぶのだと、ルークさんが教えてくれた。
いつの間にか微睡のなかにいたらしい。ドンっと床を叩く音と下品な笑い声で目が覚めて、身動ぎをする。時計を見ると、まだ三十分も経っていない。朝まではまだ時間がある。眠れるときに、眠らなければ。
小さな部屋の、小さなベッドの上。息が苦しくなるほど小さな世界で、今日も僕は身体を丸めて眠る。傷だらけの手にはめたネロリの手袋を、胸に抱いて。
この作品を共有

👏waveboxで拍手 💌フォームで感想
読んだよ!報告、感想とても嬉しいです!ありがとうございます!